今回の出張は、神山さんが「第ニ回ハクチョウ国際シンポジウム」で講演のご招待を受けたことがきっかけで、私も同行させていただくことになりました。そのおかげで、これまで行ったことのなかった山東省の東営を訪れる機会を得ました。ここには渤海湾に残された最大級の湿地と干潟である、黄河三角州があります。
このシンポジウムは、同じ時期に開催されている「Yellow River Estuary International Birdwatching Season」(黄河河口国際観鳥シーズン)の公式イベントのひとつでもあり、会議の参加者として開幕式にも出席することができました。
開幕式には、日本のほか、イギリス・韓国・モンゴルのハクチョウ研究者、鳥や湿地の保全に関わる山東省・北京等々の政府部門、そして全国の団体の方々が参加していました。また、大きいイベントだったこともあり、中国国内のメディアも多く参加していました。そして、黄河三角州鳥の映像がスクリーンに映し出され、ハクチョウやカモの姿や湿地の様子を見ることができました。その映像を見て、現地の様子を早速この目で見てみたいと思いました。

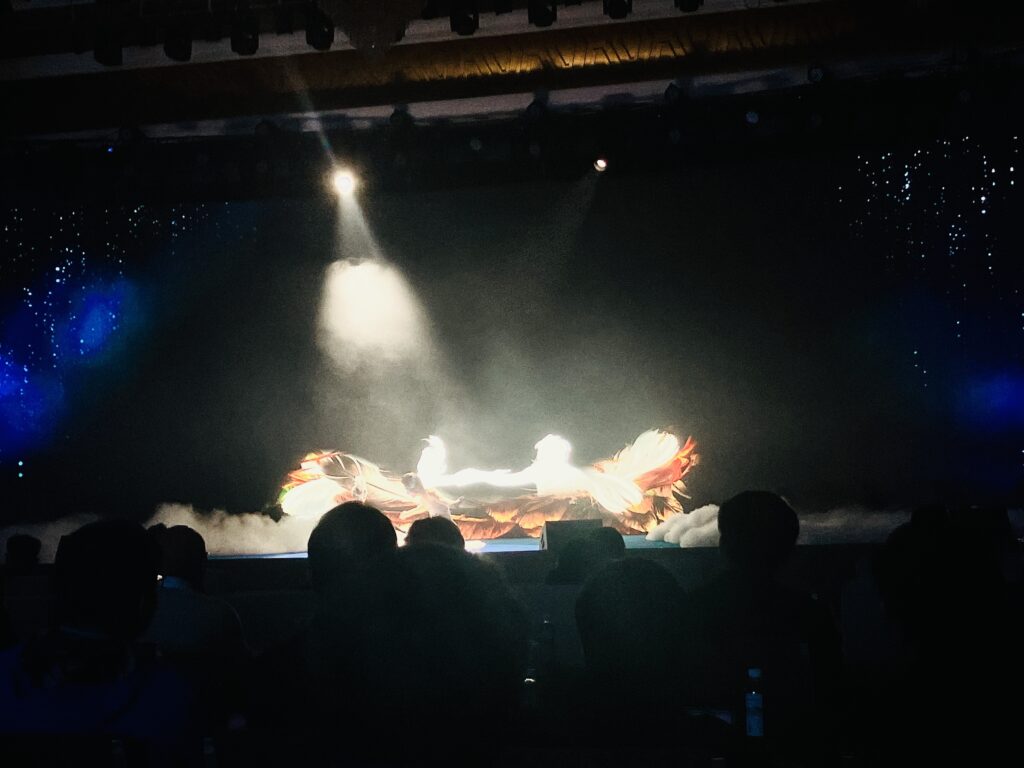
シンポジウムでの発表について
今回の出張では、偶然のご縁で私も「第ニ回ハクチョウ国際シンポジウム」で発表の機会をいただきました。そのおかげで、参加者の方々との交流を通して多くの学びを得ました。
発表後の休憩時間で、いくつかの国の研究者の方々、そして自分たちでハクチョウを守る活動を続けている市民の方々とも知り合うことができました。みなさまの思いや行動がまっすぐで、心に残りました。
また、地元の団体の方から、主人公がコウノトリの絵本『黄河口的東方白鸛(黄河口のコウノトリ)』をプレゼントしていただきました。丁寧に描かれた、とてもきれいな絵本で、大切に持ち帰りました。

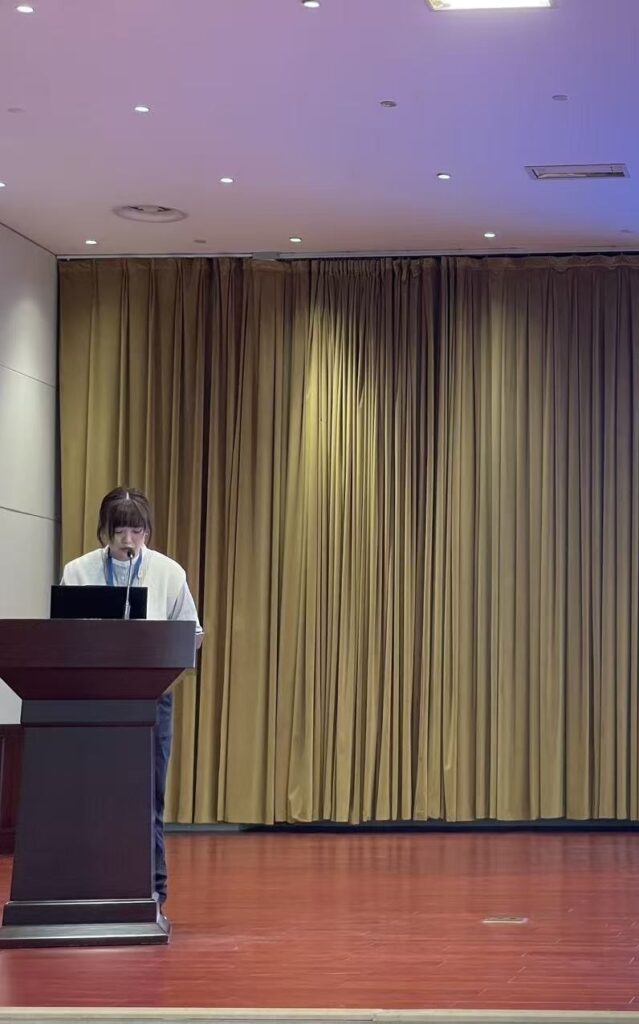

黄河三角州の見学
2日目の午前中の発表が終わったあと、皆様と一緒に黄河三角州を見に行きました。
ここでは、地元で「鳥の波」と呼ばれる、トモエガモ(現地では距離が遠くて確認できず、案内人の説明で種を知りました)の大きな群れが低空で一気に飛ぶ様子を見ることができました。とても迫力があり、印象に残りました。
その後、コウノトリのために作られた人工の巣台が整備されている場所を見学しました。そこには遊歩道があり、案内をしてくださった地元の方から「地元の人がここに来て野鳥にエサをあげている」という話をうかがいながら歩いていると、野生の鳥ではないのですが、シナガチョウが鳴きながらこちらに泳いで近づいてきました。丸々としていてとてもかわいくて、思わず足を止めてじっくり眺めてしまいました。


最後に黄河の河口を見学し、ホテルへ戻る途中、農地の上を低く飛ぶガンの群れも確認できました。

東営の街
東営に着いて最初の印象は、広い葦原、川の多さ、木にたくさんいるカササギ、そして川にいるオオバンの群れでした。市内に入ると、道が広く、明るくてきれいで、公園も多く、とても過ごしやすい街だと感じました。
今回私は、東営ハンプトン by ヒルトン ホテルに宿泊しました。到着した次の日から、韓国や日本からの探鳥ツアーの宿泊客が一気に増え、とても賑やかになりました。みなさん同じ目的で来ていたのだと思います。


黄河口国家公園について
黄河三角州に設置された黄河口国家公園には非常に広い湿地が広がっており、探鳥にとても適した場所です。
季節によってさまざまな渡り鳥が利用しており、特にハクチョウ、ガンカモ類が多いことで知られています。また、コウノトリの保全にも力を入れている場所で、電柱の上に作られた巣を見ることができます。さらに、ズグロカモメの繁殖地でもあり、繁殖期に合わせれば巣や繁殖行動も観察できそうです。そのほか、オナガ、カササギ、カンムリカイツブリも観察できました。
湿地公園内の移動距離が長いため電動カートがありますが、運転できる方は、車で回るとより多くの観察ポイントをゆっくり見ることができると思います。探鳥を目的とする方には、とてもおすすめの場所です。
旅の余談(上海での乗り継ぎ)
日本から東営への直行便がなかったため、調べてみると上海と北京の便数が比較的多いことがわかりました。今回はその中から上海で乗り継ぎすることにしました。
実は、上海に行くのは約6年ぶりでした。乗り継ぎまで時間に余裕があったので、神山さんと一緒に市内へ出て、季節の蟹みそ混ぜ麺と蟹みそ小籠包、そして最近中国で流行っている奶皮子のフルーツ飴を食べました。久しぶりの上海で、ゆっくり食事できてよかったです。とてもおいしかったです。



最後に、今回、繁殖地のモンゴル、越冬地のイギリス、日本、そして中国の研究の話を一度に聞くことができ、とても満足しました。
発表を通して、新しい技術や研究手法を知ることができただけでなく、各国がそれぞれどの点に力を入れて調査や保全を進めているのか、現在直面している課題、そして今後どのように保全を展開していくのかについても学ぶことができました。
とても勉強になり、参加できて本当によかったと思いました。ありがとうございました!

(文:姜雅珺)



